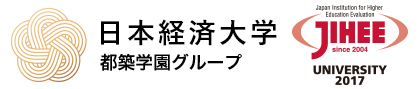こんにちは、デジタルビジネス・マネジメント学科(DBM学科)の学科長、金谷武明です。
先日、2年生向けのゼミの時間にGoogle時代の同僚だったGoogleのSearch Analyst、Gary Illyes(ゲイリー・イリェーシュ)さんが2年ぶりに来日したのでお招きし、キャリア感やデジタル業界で働くことなど様々なお話を伺いました。今回はその様子を少しご紹介したいと思います。
1. デジタル業界を目指す学生へのアドバイス
DBM学科の学生に限らず現在は多くの方が将来デジタルの仕事に関わると思います。特にDBM学科の学生はほとんどがデジタル業界に進むのではないかと思います。そこで、学生がデジタル業界で働くためにどのように備えればよいか質問してみました。
金谷「デジタル業界を目指すに当たってどんな準備をしたらいいですか?」
Garyさん「人々を研究する(Study people)ことです」
Garyさんは、技術的なスキルを学ぶこと以前に、まず「人々が何を必要としているのか」「どこで助けを必要としているのか」その本質を見つけることが重要だと述べました。例として、Google検索自体が「従来の検索エンジンに対する人々の不満(満足していなかったこと)」を解決するために生まれた、という背景を説明してくれました。
2. 学生が直面する「最大の課題」と「必要なスキル」
デジタル化が進む現代ならではの視点として、学生が直面する課題と、それに必要なスキルについても聞いてみました。
金谷「今、デジタル業界を目指す学生にとって最大の課題は何だと思いますか? また、どんなスキルを学ぶべきでしょう?」
Garyさん「最大の課題は『偽情報(misinformation)』です」
Garyさんは、ネット上には誤情報や偽情報が溢れており、何が本当で何がそうでないかを見極めるのが非常に難しくなっていることを指摘しました。
だからこそ、学生が今学ぶべき最も重要なスキルの一つは「偽情報を認識する能力」であり、それが本当かどうかを「検証(validate)する能力」だと強調していました。
ちなみに「コーディングを学ぶべきか」という点については、「もし本当に情熱があるなら」やればよいが、必ずしも全員が学ぶ必要はない、という見解でした。
3. キャリア観:「過去の自分」とどう向き合うか
講義の中では、彼のキャリア観や哲学に触れる場面もありました。特に印象的だったのが、過去との向き合い方について学生から質問が出た時です。
学生「過去の自分と今の自分を比べることをどう思いますか?」
Garyさん「私自身は過去を振り返ることはしません。それは『生産的ではない(not productive)』からです」
理由として「例えば2010年の自分と今の自分とでは、取り巻く世界も環境も違う」からだと説明しました。彼が重視しているのは過去ではなく、「今、どうするか」「次、何をするか」であり、常に未来に目を向けている姿勢が印象的でした。
4. 専門的なツールの具体的な活用法(おまけ:好きなGoogle製品)
講義の最後で、彼が個人的に気に入っているGoogle製品についても聞いてみました。
金谷「好きなGoogle製品は何ですか?」
Garyさん「(検索、Gmail、Driveは当然として)Notebook LMです」
Garyさんは、仕事で「70ページにも及ぶ科学的な出版物(論文など)」を読まなければならないことがあり、その際に、Notebook LMがいかに役立つかを熱心に語ってくれました。
単に要約するだけでなく、特定の情報について(その資料に基づいて)AIに質問をすることで、膨大な資料を読む時間を大幅に短縮できる、という具体的な活用法は、学生にとっても非常に実用的で興味深い内容だったと思います。
DBM学科の2年生はGoogleの日本法人を訪問したり、Googleから講師を迎えている講義を受講したり、9月の留学に参加した学生は海外のオフィスで働く日本人のGoogle社員と交流するなど色々Googleとの接点はありますが、今回海外で働く日本語を母国語としないGoogle社員の話はとてもおもしろかったようです。沢山の感想を頂きましたのでちょっと長くなってしまいますが、ご紹介したいと思います。
学生の感想
「ゲイリーさんのお話の中で私にとって印象的だったのは、自身の興味に対する向き合い方である。興味を持った食べ物や文化があれば、その起源を詳しく調べて実際に現地まで足を運ぶというエピソードを聞き、その行動力と知見の広げ方に強い関心を持った。また、「過去にはない価値観や知識を今は持っているから、思い出以外の過去は振り返らないよ」という言葉にも、常に進化していく姿勢を感じ、強い尊敬を抱いた。」
「アメリカ留学に行った際、いろいろな価値観や日本と異なる文化に触れて自分の世界が広がっていったことで、英語を話せるようになりたいと強く思い英語学習に取り組んだが、英語を話せるようになることは簡単ではないため、すぐに成果が出ずモチベーションを維持することがむずかしかった。留学中に訪問したGoogle本社では、お話しさせていただいた方は現地の日本人社員の方々だったため、言語の壁を感じることが少なかったが、今回の機会で、気さくなゲイリーさんのジョークや、話の中の感情やニュアンスを直接感じ取れない時に、もったいないと強く感じていた。
この学科では、先生のお知り合いで、企業の社長やGoogleの社員の方々といった、普段お会いできない方々から直接お話を聞ける貴重な機会が多くあり、ゲイリーさんの話もその貴重な機会の一つだった。
この貴重な機会が「英語が話せない」ことで不自由になっていると考えた時、自分の世界を狭めていることに気づいた。
ゲイリーさんから学んだ知的好奇心と行動力を見習うと共に、「もったいない」と感じたことで得た英語学習へのモチベーションを生かし、日々努力していこうと考えている。」
「デジタル化が進む現代では、情報があふれ、正しいことと間違っていることの境界がとても曖昧になっていると感じます。動画の切り取りやAI技術によって、事実が簡単に歪められる時代だからこそ、何が本当で何が偽物なのかを見分ける力がますます大切になっています。ゲイリーさんがそのような時代の中で、人々に正しい情報を伝えようと努力していることに深い尊敬を感じました。」
「今回のお話を聞いて、外国の大企業で活躍する人の考え方や姿勢に触れ、勇気をもらいました。私は今まで、うまくいかないことが怖くて挑戦を避けてしまうことがありましたが、実際にやってみると、思っていたほど大したことではないと気づくことが多いです。これからは完璧を求めすぎず、一歩ずつ成長していきたいと思いました。」
「今日の講義でいちばん印象に残ったのは、ゲイリーさんが話してくださった「人のためになる技術とは何か」ということです。検索エンジンは昔から今のように便利だったわけではなく、Googleは人々の行動をよく観察して、どんなときに満足しているかを考えながら改良してきたと聞きました。その話を聞いて、技術の中心には「人を理解すること」があるのだと感じました。」
英語での講義となり、伝わったか色々不安はありましたがコメントを読む限りではとても良く伝わっていたようでとても嬉しいです(講義では金谷が通訳しながら行いました)。
今後もこうした機会を通じて、学生たちの視野を広げ、彼ら彼女らの未来を切り拓くサポートをしていく所存です。
金谷武明(デジタルビジネス・マネジメント学科 学科長)